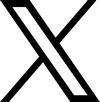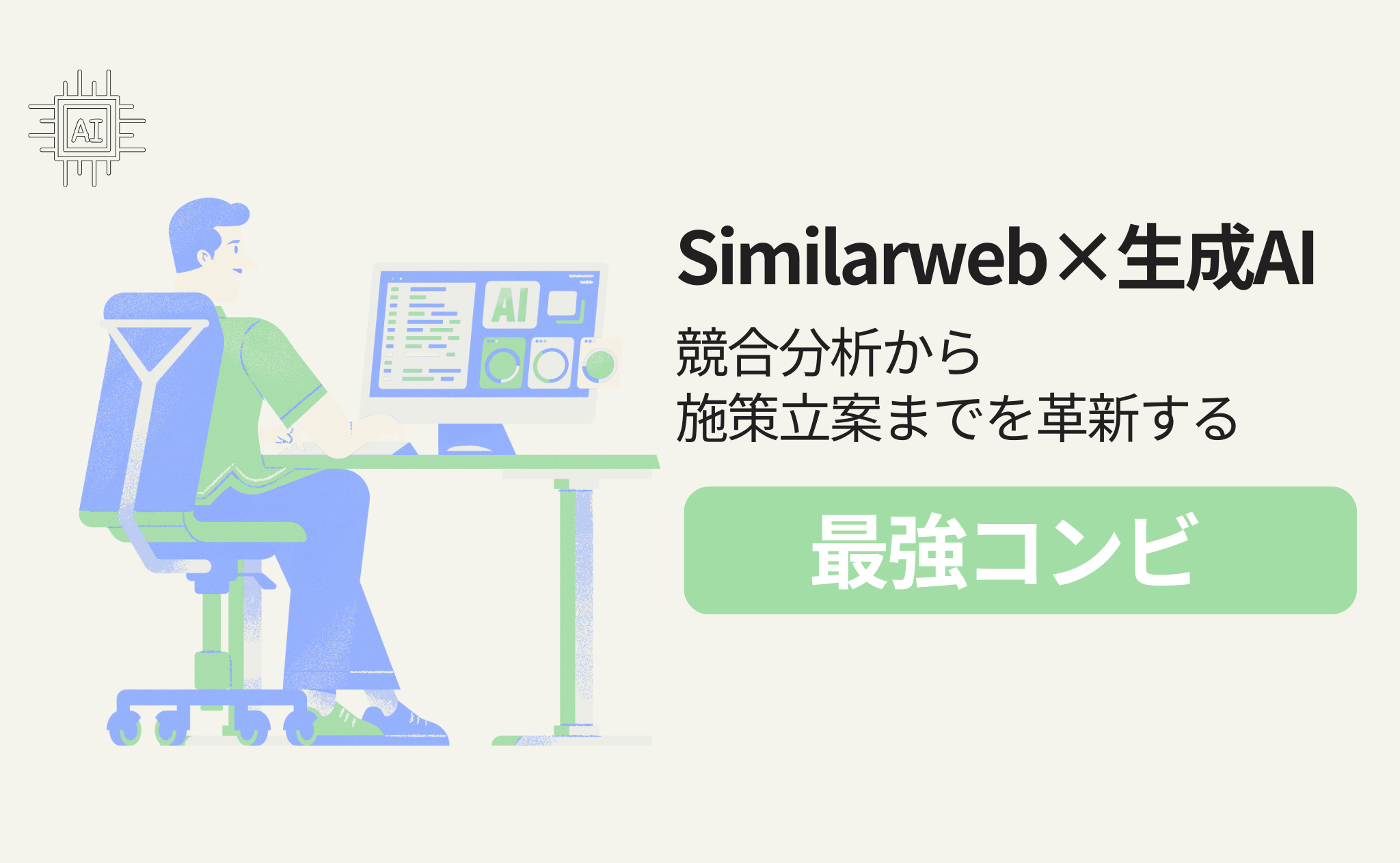【舞台裏公開】トップマーケターが実践するデータドリブン戦略動画、制作秘話と想い
なぜ今、データドリブンマーケティングなのか?
近年、AI技術はめざましい進化を遂げており、特にマーケティング分野では、従来の手法だけでは対応しきれない場面が増えてきました。たとえば自社データだけでは、お客さまがどこで迷っているのか、競合にどの程度流れているのかといった"リアルな行動"までは見えてきません。さらに、分析には担当者の経験や勘に頼る部分も多く、「なぜそうなるのか?」という背景まで正確に捉えることが難しい──。こうした構造的な課題を、多くの企業が長年抱えてきたのではないでしょうか。
そんな中、フューチャースピリッツではSimilarweb Japanの清水様をお招きして、「【トップマーケターはもうやっている!】Similarweb × 生成AI/最強のデータドリブン戦略を徹底解剖/競合比較・可視化・勝ち筋設計のすべて」という対談動画を公開いたしました。
正直なところ、企画段階では「本当に視聴者のみなさんに価値を提供できるだろうか」という不安もありましたが、実際に制作を進めていく中で、これまでにない新しいマーケティングの可能性を感じることができました。
企画段階:課題解決と共創への想い

今回の企画は、フューチャースピリッツとSimilarweb Japan様の共催という形で進めさせていただきました。企画会議では何度も「本当に視聴者の方々の課題解決につながるのか」という議論を重ねました。最終的に、リード獲得を主目的としながらも、無料相談やワークショップへの関心を高めていただき、実際のビジネス成長に貢献したいという想いを込めました。
ターゲット層として想定したのは、中小企業のマーケティング担当者のみなさま:
- ベンダーとの連携に悩まれている方
- 競合分析やカスタマージャーニー設計に関心をお持ちの方
- Similarwebは知っているけれど、その数字の意味や活用法に迷われている方
- マーケティング業務の効率化と人的工数削減を目指されている方
企画段階で印象的だったのは、清水様との打ち合わせで「単なるツール紹介で終わらせたくない」という共通認識を持てたことでした。データドリブンマーケティングの本質的な価値をお伝えしたいという想いが、両社で一致していたんです。
撮影機材と技術的なこだわり:品質への徹底追求

今回の撮影では、機材選びから設定までこだわりました。やはり映像品質は視聴者の方の体験に直結すると思います。
撮影機材の選択理由
メインカメラには、SONYのα7R5を使用しました。このカメラを選んだ理由は、高解像度でありながら長時間撮影での安定性と発色の良さを両立できるからです。レンズは50mm単焦点レンズのみで撮影しました。ズームレンズも検討したのですが、単焦点の方が画質が安定し、対談という性質上、自然なパースペクティブと被写体の表情・空気感をしっかりと捉えることができると判断しました。三脚を立てて固定撮影することで、ブレのない安定した映像を心がけました。
音声収録へのこだわり
音声には、Anker WorkのワイヤレスマイクM650を使用しました。登壇者それぞれにマイクを装着いただき、クリアな音声収録を実現しました。実は音声品質については制作チーム内でも特に議論が多かった部分で、「せっかく良い内容でも音が悪いと台無しになってしまう」という懸念がありました。そこで、カメラ本体のほか、マイク本体にもバックアップとしてデータを保存する二重の安全策を取りました。結果的に、この判断が功を奏して、クリアな音声を確保できました。
撮影設定の工夫
フレームレートは60fpsに設定し、滑らかな映像表現を追求しました。シャッタースピードは120の設定がなかったため、フリッカーレス機能を使い、近しい値で調整しています。今回は長時間の対談撮影だったため、データ容量とのバランスを考慮して画質はHDで設定しました。4Kでの撮影も検討したのですが、編集作業の効率性と最終的な配信品質を総合的に判断した結果です。
編集プロセス:地道な作業の積み重ねと想いの込め方
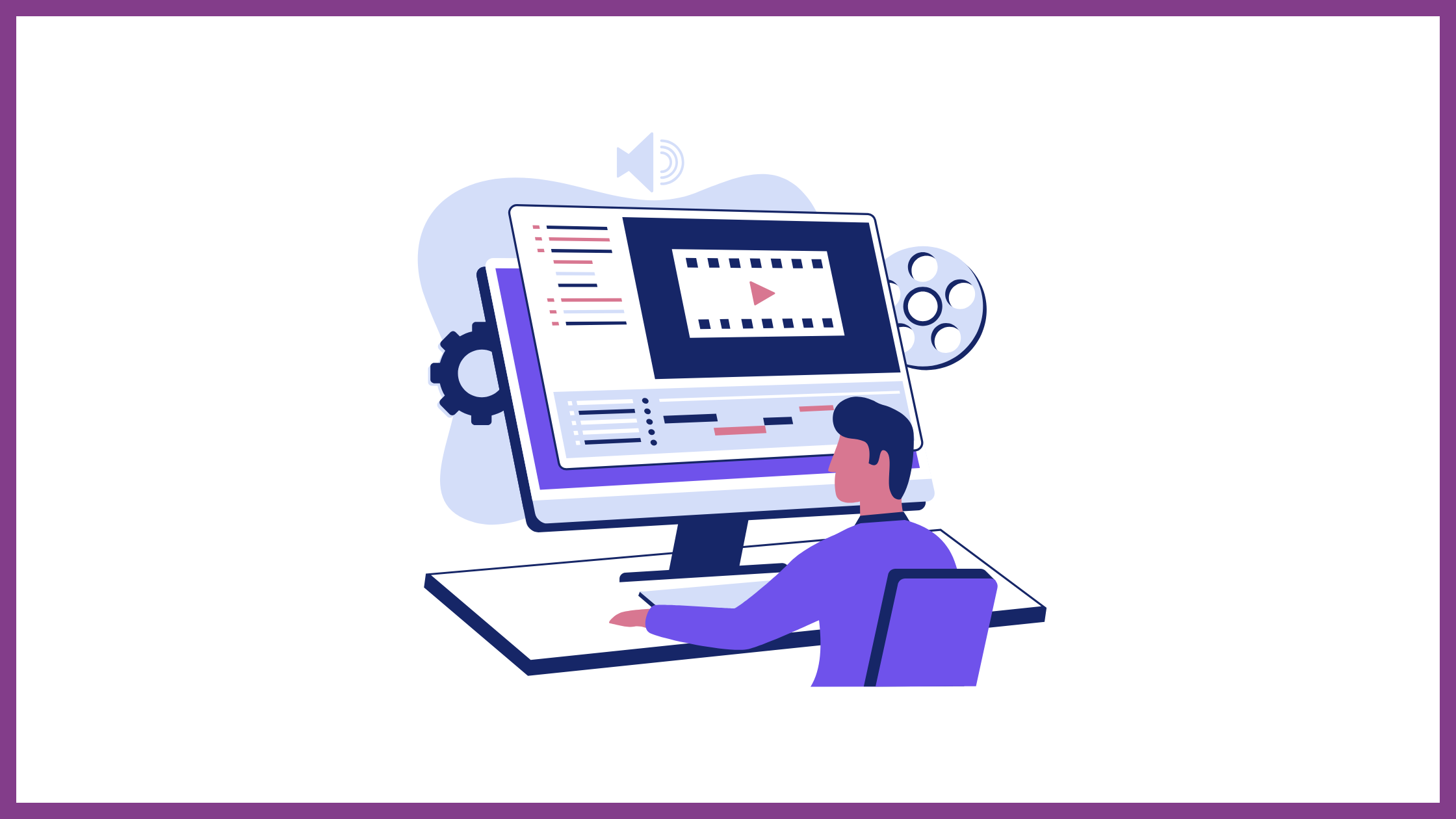
編集作業は、正直なところ想像以上に時間と労力がかかりました。でも、その分だけ視聴者の方により良い体験を提供できるのではないかという想いで取り組みました。
音声処理の工夫
まず、別タイムラインに左右のマイクの音声をセットしました。編集で音声をデュアルモノ(2chに分けたモノラル)として処理することで、どちらの登壇者が話しているかを明確にし、聞き取りやすさを向上させています。カメラで撮影した対談人物のカットを主として、Zoom録画した資料映像をマスク機能でセットして、人物が資料の上に自然に重なるような構成にしました。
編集工程の詳細
編集は段階的に以下の流れで進めました:
1. 素材のベース作り
まず「えー」とか「あー」といった声部分をカットしたり、NG部分をカットしたりと、とにかくカット作業の連続でした。この作業は本当に地味で時間がかかるのですが、最終的な視聴体験を考えると欠かせない工程だと感じています。
2. 音声バランス調整
左の方が話している時には左の音声を大きく、右を小さく。右の方が話している時は右を大きく、左を小さくという、これまた地味な作業でした。でも、この細かい調整があることで、視聴者の方が「今誰が話しているのか」を自然に理解できるようになります。
3. カラーグレーディング
素材のベースが完成すると、映像全体の色調整に取り組みました。実は、ちょうど良いLUTが見つからなかったので、独自で設定することになりました。これは予想外の作業でしたが、結果的に動画全体の統一感が出せたのではないかと思います。
4. 資料表示とテロップ追加
マスク機能で資料を表示し、重要な部分にテロップを追加しました。テロップ作成では、「どの部分が本当に重要なのか」を何度も検討し、視聴者の方の理解を助けるポイントに絞って追加しました。
5. 効果音と演出
効果音も適切なタイミングで追加し、視聴体験の向上を図りました。
6. オープニング制作
動画撮影時に併せて撮影しておいた写真素材を活用して、視聴者の方を引き込むようなオープニングを作成しました。最後に最終の音声調整とミキシングを行い、書き出しを完了しました。
サムネイルについても、動画撮影時に併せて撮影しておいた写真素材が複数あったので、本当に助かりました。サムネイルは動画の「顔」とも言える部分なので、複数の選択肢があることで、より効果的なものを選べたと思います。
コンテンツの核心:Similarwebと生成AIの相乗効果

動画の構成を考える際に最も重視したのは、「視聴者の方が明日から実践できる内容にする」ということでした。理論だけでなく、具体的なアクションまで落とし込める内容を心がけました。
動画のアジェンダは以下の4つで構成しています:
1. ゼロ次分析について
これは個人的にも非常に興味深い概念でした。自社データだけでは見えない潜在層を発見し、競合分析から仮説を構築するという考え方は、まさに「目から鱗」でした。実際の事例で、ECサイトが新規コンテンツ導入後3ヶ月で自然検索流入が40%増加したという話は、制作チーム内でも大きな話題になりました。
2. トレンド分析の革新
市場の変化を素早く察知する手法については、BtoBサービス企業でセミナー登録が68%増加した事例が特に印象的でした。数字だけでなく、その背景にあるユーザー心理まで理解できるというのは、マーケターとして非常に魅力的だと感じました。
3. Similarwebと生成AIの相乗効果
ここが今回の動画の核心部分だと思います。意思決定の高速化、仮説の質向上、施策バリエーションの拡大、チーム内共有の質向上といったメリットは、企業のデジタルマーケティングによる新規獲得やLTVアップにも大きく貢献するはずだと確信しています。
4. 導入事例と実践ガイド
具体的なプロンプト例の紹介では、制作チームでも「これなら明日から使える」という声が多く上がりました。
制作プロセスと工夫:実践とリアルタイム性へのこだわり

動画の収録では、対談形式を採用しました。スライド資料も用意しましたが、何より大切にしたのは「視聴者の方が自分の課題として捉えられるか」という点でした。
制作過程で特に工夫したのは、Microsoft ClarityやGenspark(生成AIツール)を使った実際のデモンストレーションです。正直、最初は「うまく動作するだろうか」という不安もありましたが、実際にツールを動かしながら説明することで、視聴者の方により深く理解していただけるのではないかと考えました。Similarwebで競合キーワードを抽出し、それを生成AIに投入してペルソナ像やコンテンツ案を生成するプロセスは、実際にやってみて「本当に使える」と実感できるものでした。
データプライバシーの話題では、制作チーム内でも活発な議論がありました。Google Analyticsのデータには個人情報に近いものが含まれる可能性があるため、AIへの投入は推奨されない一方、Similarwebのデータは個人を特定する情報を含まないため、AIとの連携において安全性が高いという点は、私たちにとっても新しい発見でした。
また、プロンプト設計の質の重要性については、実際に何度もテストを重ねました。構造化された指示、具体的なデータ提供、出力形式の指定といったコツを実践してみると、確かにAIの出力品質が格段に向上することを実感できました。
公開後の展望:未来のマーケティングへの期待

動画の最後で触れた未来の展望については、制作チーム一同、非常にワクワクしながら議論しました:
- AIによる予測精度の向上では、業界別・商材別の予測モデル自動生成の可能性
- クロスプラットフォーム分析では、WebだけでなくSNSやアプリ、実店舗データまでの統合分析
- 自動最適化システムでは、分析から実行までをAIが支援する未来
これらの未来に向けて、企業には「データサイエンティストとマーケターの協業体制強化」「AIリテラシー向上のための社内教育」「データ駆動型意思決定を評価する組織文化の醸成」といった準備が必要だと感じています。
最後に:視聴者の皆さんへの想い
今回の動画制作を通じて、改めて感じたのは「品質の高いコンテンツを作るには、技術的な部分も含めて妥協できない」ということでした。撮影から編集まで、一つひとつの工程に時間をかけることで、視聴者の方により良い体験を提供できるのだと実感しています。
今回の動画では「30日チャレンジ」という具体的なアクションプランもご提案させていただきました。Similarwebのテストアカウントを使って、実際に競合キーワードや市場キーワードを分析し、生成AIでペルソナを作成する体験をしていただければと思います。
制作を通じて感じたのは、マーケティングの世界は本当に日進月歩で進化しているということです。でも、その中心にあるのはやはり「お客さまのことを深く理解したい」という想いなんですね。今回の動画が、視聴者の皆さんのマーケティング活動に少しでもお役に立てれば、制作チーム一同、これ以上の喜びはありません。
ぜひ、動画をご覧いただき、みなさんの率直なご感想やご質問をお聞かせください。今回の動画制作では、コンテンツの価値だけでなく、制作への想いと技術的なこだわりも込められています。マーケティングの未来を一緒に考えていけるような、そんな動画になったのではないかと思います。今後も「ヨリミル-yorimiru-」では、現場に役立つリアルな情報をお届けしてまいります。
-
資料請求
ヨリミルのサービス資料をダウンロードいただけます。
ノウハウをお役立ち資料として無料配布しています。 -
無料相談
課題感が明確でなくても構いません。
まずはお気軽にご相談ください。 -
メルマガ登録