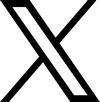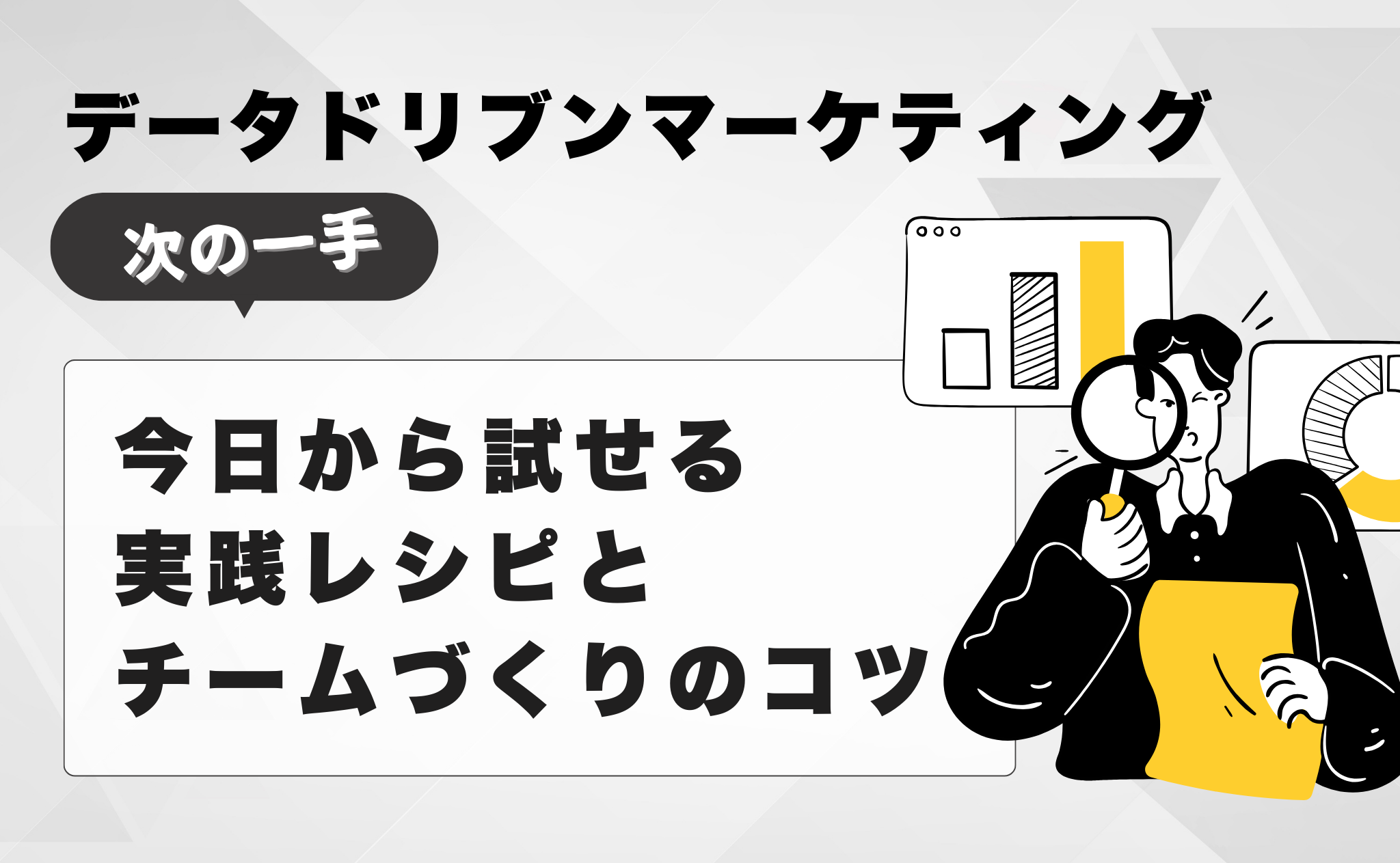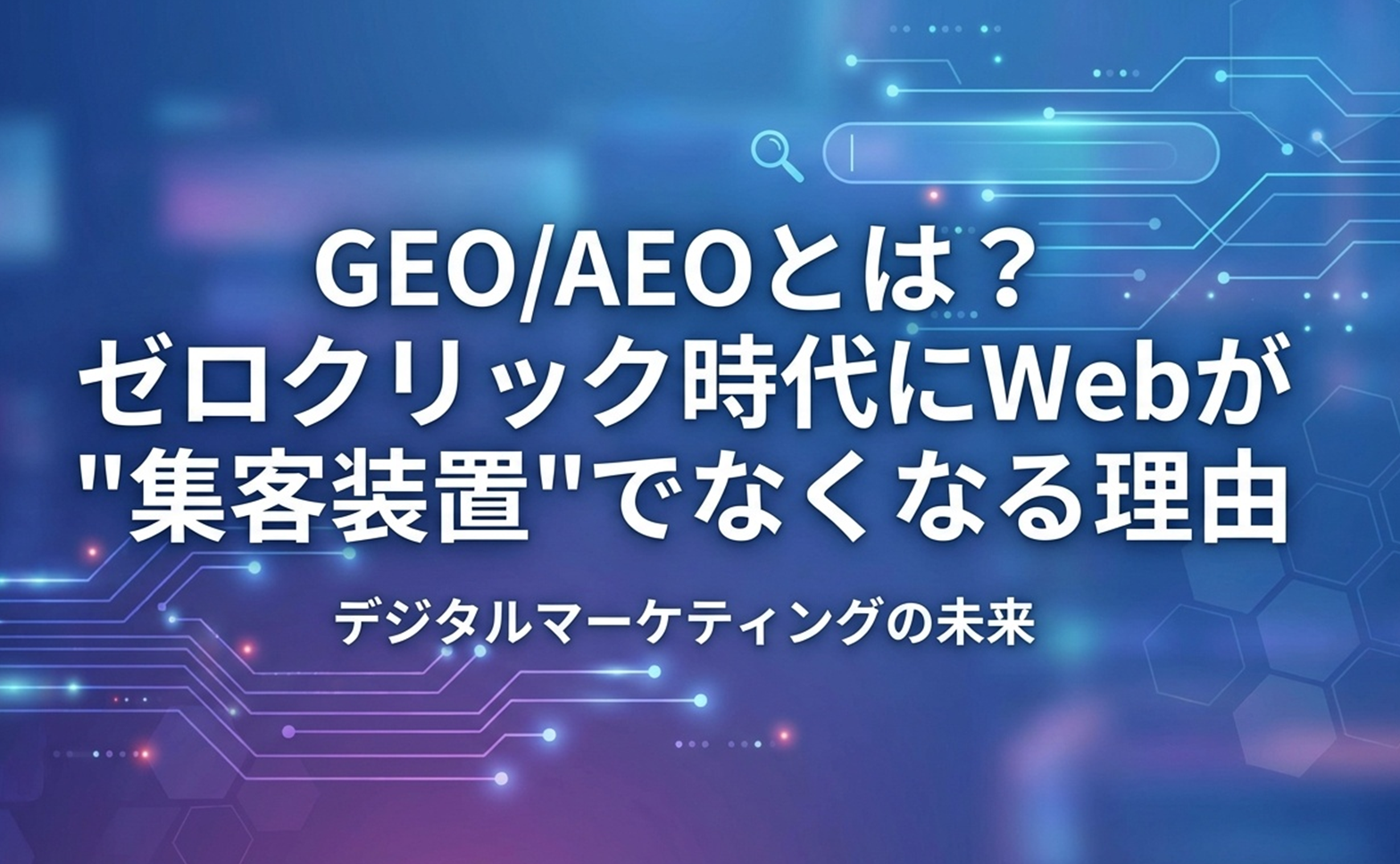土日も働いていた僕が、生成AIで"自由時間"を取り戻した話
はじめに:生成AIの進化と書き手の葛藤
どうも、ヨリミルライターの須賀です。
ここ最近、生成AIの進化スピードは、まさに尋常ではありません。
昨日できなかったことが今日はできるようになり、逆に、昨日までできていたことが突然制限される。
そんな変化が、もはや日常になっています。
だからこの記事も、読むタイミングによっては内容が少し古く感じられるかもしれません(※執筆時:2025年10月10日時点)。それでも今回は、「機能紹介」や「チュートリアル」ではなく、生成AIをどう体験し、自分の働き方をどう変えたのか。
そのリアルな実感を、率直に綴ってみたいと思います。
AIがくれた"自分の時間"という感覚
僕はもともと、プロデューサー/営業的な立場で、複数の案件を同時に走らせています。
打ち合わせ・資料作成・説明・調整。そんな日々の繰り返しでいつの間にか「土日も働くのが当たり前」になっていました。(ちなみに、マネジメントというやつもあります)
そんな中、生成AIを仕事に取り入れてみたら、驚くほど時間の使い方が変わりました。
AIが作業を代わってくれるというよりは「自分がやるべきことの質」が変わった感覚です。
たとえば、打ち合わせのための資料をAIと一緒に整理したり、会話内容を動画+文字起こしで共有したり。その結果、「説明に使う時間」が減って、「議論に使う時間」を増やせるようになりました。
そして気づけば、平日夜や週末に やりたいことの時間が、少しずつ戻ってきていたのです。
会議を「減らす」ではなく「磨く」
以前の僕は、MTG(ミーティング)があまり好きではありませんでした。
僕のことを知る人は「えっ?」と思うかもしれませんが、目的が明確なときは全力でやります(笑)逆に、目的が曖昧な会議ほど、人の時間を奪ってしまうものだと感じてました。だから、案件のMTGは必要最低限で。勉強会的な場や情報共有の時間は、必要に応じて行っていたという感じでした。
でも、生成AIを活用し始めてからはそのやり方が少し変わりました。
会議の前に、AIでまとめた「説明動画」や「要点資料」を先に共有しておく。
そうすることで相手は自分のタイミングでそれを確認できるし、MTG当日は質問と議論に集中できる。
たったそれだけで、生産性がまるで違います。
AIが「説明の下地」を整えてくれることで、人と人の時間が本来の価値を取り戻した気がしています。
AIを「使う」のではなく、「一緒に考える」
多くの人が、AIを「調べ物をするツール」として使っています。
もちろんそれも便利。でも、僕にとってのAIは考える相棒(エージェント)のような存在です。
たとえば提案資料を作るとき、AIに「質問してもらう」ように設定して壁打ち相手になってもらいます。不足している視点や、想定されるツッコミをAIが投げかけてくれるので、事前に答えを準備することができる。
その結果、提案内容がより深まり、相手との会話もより専門的になっていきました。
頼るというより、AIと一緒に思考の筋トレをしている感覚に近いかもしれません。
だからこそ、AIを使いこなすコツは「命令すること」ではなく、「対話すること」だと思っています。
仕事量は増えた。でも作業量は減った
おもしろいことに、AIを活用するようになってから、むしろ案件の数は増えました。
でも、不思議と作業の負担は軽くなっているんです。
たとえば、AIが議事録を自動でまとめてくれたり、提案資料のたたき台を作ってくれたり。その分、僕自身は「考える時間」や「新しいアイデアを形にする時間」に集中できるようになりました。
最近では、自分でAIエージェントをつくることもあります。
たとえば、「カスタマージャーニーをURL入力で自動生成するGPTs」や、「ナラティブストーリーを構築するGPTs」など、これまで人の感性が必要だと思われていた領域にも、AIと共に検証してチャレンジできるのが面白いところです。
もちろん、正解はないかもしれません。でも、だからこそ試してみる価値がある。
挑戦することで、見えてくるものがあると信じています。
趣味で触れて、仕事に返す
僕は音楽や映像づくりが好きで、仕事終わりや休日にAIを使ってミュージックビデオを作ったりしています。Sora2やVeoなどの動画生成AIを試してみると、「AIの得意・不得意」や「プロンプト設計のコツ」が肌感覚で分かってくるんです。
その体験を仕事に応用すると──
「どう伝えれば、AIが狙い通りのアウトプットを出してくれるか」
「どんな構成にすれば、映像のトーンや世界観が一貫するか」
といった精度がぐっと高まります。
つまり、趣味での試行錯誤が、仕事の精度を引き上げてくれる。
これも、AI時代ならではの健やかな循環のひとつだと思います。
ちなみに、この動画のはじまりや終わりに流れる短い音楽ジングルも、実は自作してみました。
(弊社サービス「Movable Type Premium」の紹介動画です!)
自分の趣味で、MV(ミュージックビデオ)用の映像を動画生成AIでつくってみたり。
"偶然の出会い"を楽しむ余裕
AI生成動画の面白さは、同じプロンプトを入れても、毎回違う結果が返ってくるところ。
狙った通りにいかないからこそ、思いがけない表現に出会える──この"偶然性"が、まるでアートに近い。
そんな小さな発見を楽しめるようになったのは、
AIに作業を任せたことで、自分の頭と心に「余白」が生まれたからかもしれません。
まとめ:AIがくれたのは「自由に考える時間」
生成AIは「効率化の道具」として語られがちですが、
僕にとっては、自分の思考を深める時間を取り戻してくれる大切なパートナーです。
AIを取り入れてから、
・打合せは短く、でも内容は濃く
・資料づくりは早く、でも精度は高く
・そして、夜は自分の好きなものをつくる時間へ
そんなふうに、"自由時間"が少しずつ戻ってきました。
AIが僕の仕事を奪うことはなかった。
むしろ僕の時間を、取り戻させてくれたのだと思います。
おわりに
AI時代の働き方に、「これが正解」というものは、まだありません。
でも、自分の経験からひとつだけ言えるのは生成AIは、"人の可能性"を広げてくれるツールだということ。
今日もまた、AIと会話しながら、新しいアイデアをかたちにしています。
その積み重ねこそが、僕にとっての"ホワイトな働き方"なんだと思います。

以下、あとがき
ここからは、動画を作成してみて気づいたことを日記メモとして綴ってみます(笑)
Sora2で気づいたこと
-
画像を引用して動画生成すると、ウォーターマークがついてしまう。
プロンプトだけで生成した方がきれい。 -
Pro版でも1本最大15秒しか作れない。各動画が独立しているため、同一人物が登場する一連のストーリー構成はできない。
→ 登場人物を統一したい場合は、他の動画生成AIの方が向いてる。
どうしてもPro版で完結させたい場合は構成を見直し再考する。
Veo3.1では?
-
作成コスト(クレジット消費量)も含めて要検証中。
-
10秒動画をつなげて構成する際、カメラワークやトーンの統一が難しい。
共通のプロンプト設計が重要。
作って気づくプロのすごさ
動画作成を進めるほど、「プロが普段やってくれている調整の細やかさ」が身に染みます。僕らが「こういう感じで!」って一言でお願いしてる裏では、膨大な試行錯誤があるんだなと、実感しました。
プロンプトの壁
-
最近は日本語対応も進んでますが、やはり英語プロンプトの方が精度が高い。
-
ただし、日本語→英語への単純翻訳だと意図がズレることも多く、精査が必要。
絵コンテとの連携
生成AIと一緒に絵コンテも作ってみましたが、思い描いているものと少しズレてる場合、プロンプトの細分化や再設計が必要。ただ、やり取りを重ねていく中で、AIが文脈を引き継いでくれるのは驚き。
(※Gensparkのスーパーエージェントはこの点で特に優秀です)
一期一会の動画たち
同じプロンプトを入れても、毎回違う動画が生まれる。
これは生成AIの「面白さ」でもあり「運ゲー」要素でもあります(笑)
だからこそ、
-
「自分が何を表現したいか」という明確な意図が必要。
-
でも、思いがけない「めっちゃ良いやん!」との出会いもある。
-
ダメな仕上がりだった時の落胆に打ち勝つ、折れない心も必要。
最後に
「理想通りの動画を作りたいなら、やっぱり実写で撮影する必要があるな」とも感じました。
でも、「想いをカタチにする一歩目」として、生成AIで試してみるのはすごく価値がある。しかも、生成AIは進化のスピードが日々すごい。
今日できなかったことが、明日できるようになっている。
そんな未来を体感しながら、僕はこれからもいろんな動画をつくっていきたいと思います。
-
資料請求
ヨリミルのサービス資料をダウンロードいただけます。
ノウハウをお役立ち資料として無料配布しています。 -
無料相談
課題感が明確でなくても構いません。
まずはお気軽にご相談ください。 -
メルマガ登録