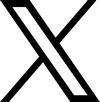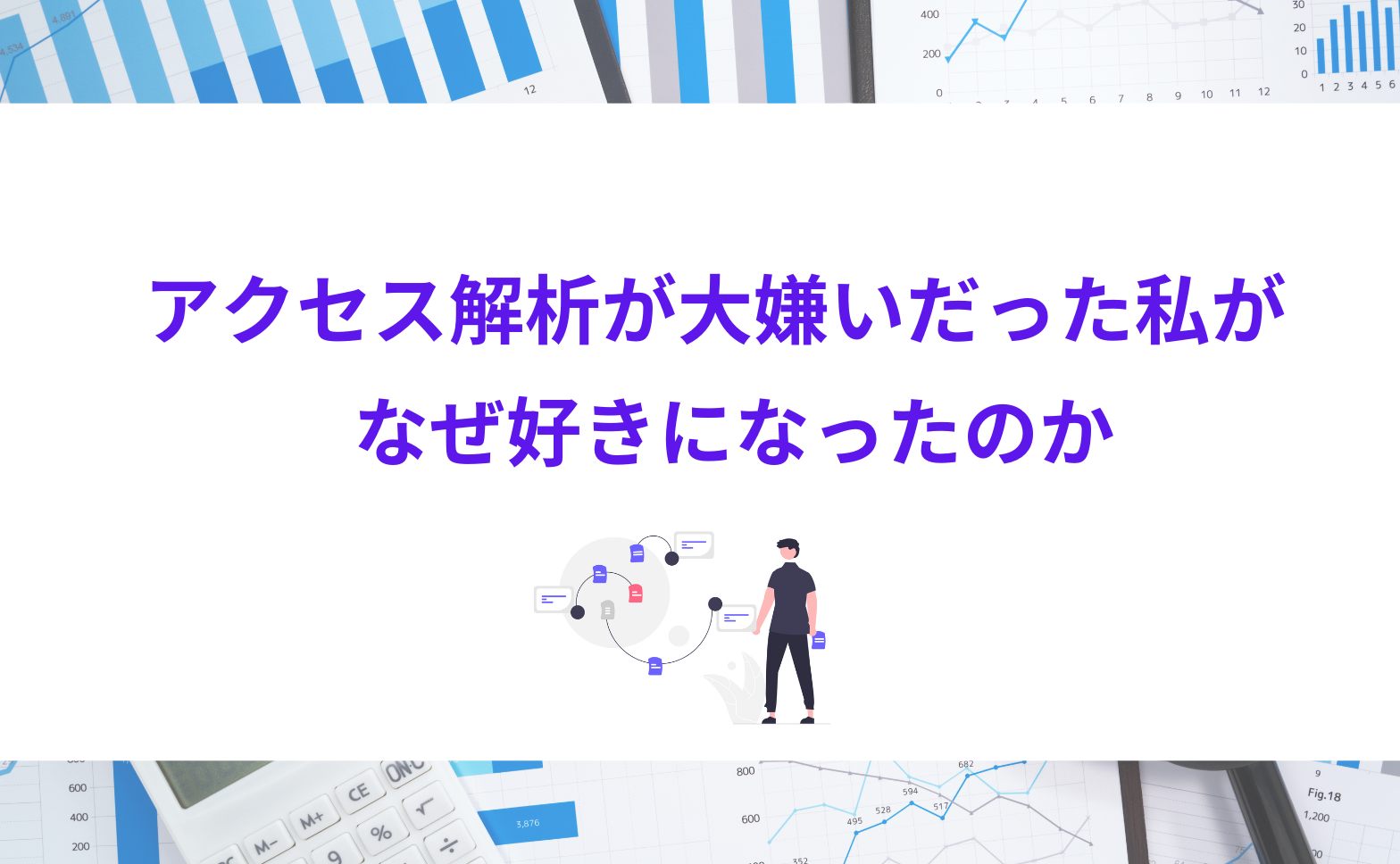Clarityとは?CXを深掘りするための重要なポイント
Microsoft Clarityってご存じですか?
何かを新しいものや気付き、発見なんてきっかけはある日突然ですよね。
しかも、そういうものって探してる時になかなか見つからなくて、なんてことないふとした瞬間に出逢うものだったりしませんか?
ラブストーリーは突然にぐらいに、衝撃的な出逢いが僕とClarityとの出逢いでした。
「これは...今までのユーザーテストなどの在り様がゴロっと変わるぞ...」と、新しい扉が開いたようなそんな感覚になりました。
色んなお客様に見せながらご説明してるといつも「こんなこと見えるんですね...」と一緒になって驚いてもらったり、これがあったら...こういう風に考えれますねといった話に繋がっていく事が多く、「Web行動の検証」をする際にはGA(Google Amalytics)などのレポートの数字では詳細まで分からない部分をこのツールが補ってくれるというものになります。
ただ、Clarity、使ってる方々ってどのぐらいいるんでしょうか?
割と色んな会社さんにてお話してる時にも知らなかったみたいなお声も多く、是非是非皆さま上手く活用してもらったら良いなと思ってこういう記事を書いてみようと思いました。
CX(顧客体験)を知る為のツールとしてのClarity
皆様、これまでに色んな角度で「顧客行動」であったり「顧客体験」を知ろうとして色んな取り組みをしておられたかと思います。私もその一端にもおりますし、その行動分析に於いてはWebに於いてはそれこそGoogle Analyticsの経路データとにらめっこしたり、重点項目をKPIとして指標化して改善考えたり、クリックイベントの数値をレポートとして追いかけたり、ヒートマップで確認したり...。
顧客行動としてはカスタマージャーニーなどから行動を想定したり、アンケートやインタビューなどで実際の顧客の声を拾って調べたり。
そんな行動を知るという時に、これまでは直接お客様のお客様(エンドユーザー)にお願いをしたりして、「ユーザーテスト」という手法も行ってまいりました。

クライアント様のご厚意で、調査会社さんの調査レポート報告などを一緒に拝聴する機会などもあったりするのですが(聴いてもらって意見欲しいとか、そういう結果を踏まえて施策として何か考えて欲しいとかそういうご相談があります)
アンケートやユーザー調査結果というのが、報告を聞いててもどうも「調査対象者が本当にこのサービス使ってるのかな...」という回答で報告されることも度々見受けられておりまして(例えば、アプリを使った情報発信はしてないが、御社のアプリの使い易さの評価として高い!とか...)、そのたびクライアント様からは「多分、アンケートだから答えてくれてるユーザーは本当に使ってる利用者以外も入ってそう」という声もお聞きしたりしますし、定量調査あるあるなのかもしれませんが結構どうなんだろうな...って悩ましい結果が出てくるケースも少なくないのです。
そして、ユーザーテストという調査手法です。
これは、我々も実施していますし、よりクライアント様の利用ユーザーと想定ペルソナに沿ったアサインをして、ユーザーシナリオを考え、発話法という手法でテストとして行います。
勿論、すごい気付きあります。その瞬間、何を感じてどう思ってるのか。
それこそカスタマージャーニーなどを行った上でのユーザーとのコンタクトポイントとして整理された状態であれば想定されるテストケースも非常に明確なので「こういう行動を行ってみてください」というオーダーをさせていただき、実際の動作を行っていただくので見えるものも気付きも多くあります。
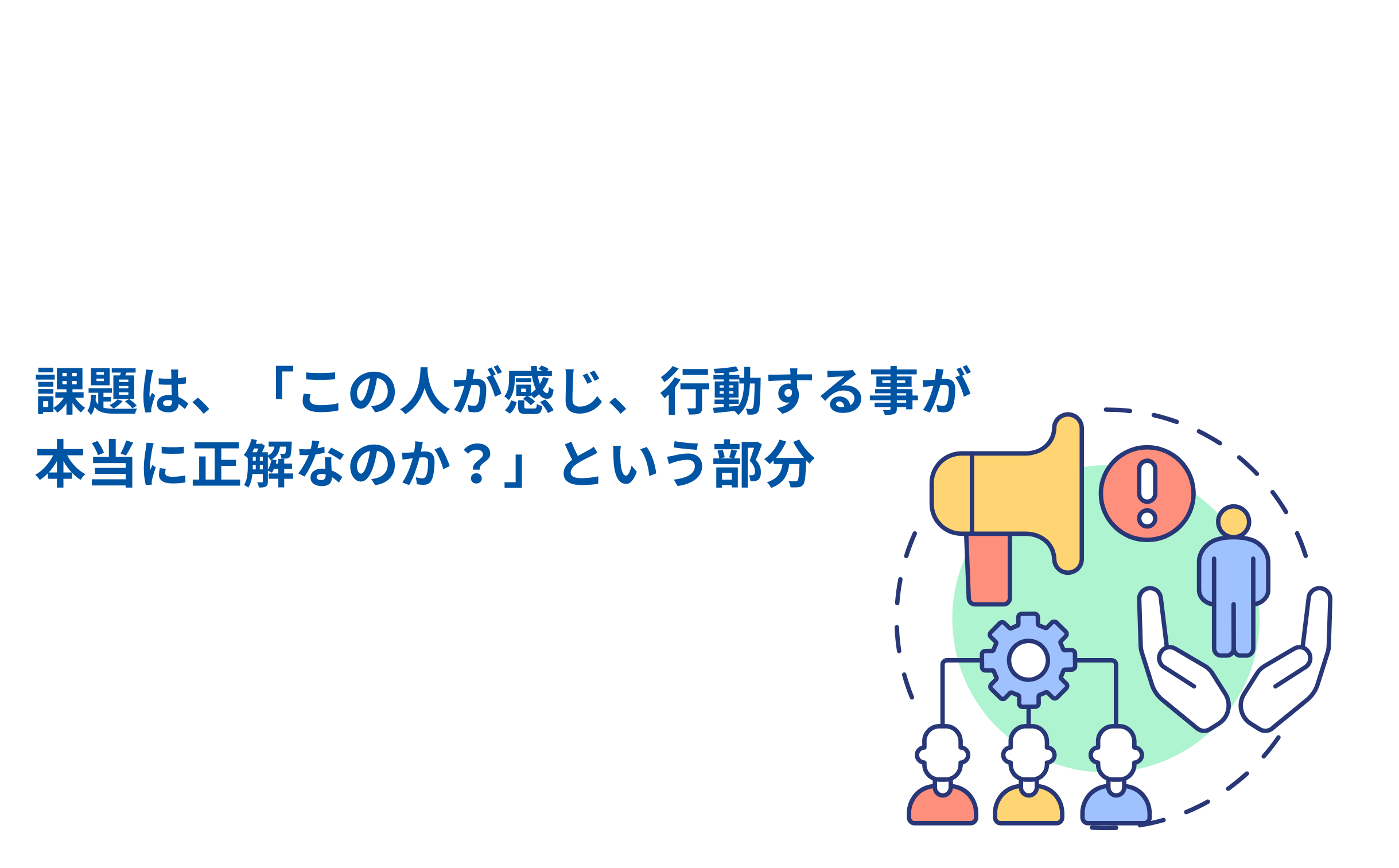
これは、カスタマージャーニーのワークショップを行い、ペルソナを想定する時にもそうですし、こういうユーザーテストを行う時に選出するテストユーザーに於いてもそうなのですがこの人だからこそこう感じた。というものもテストをした結果として報告していくので「この人の場合のケースは・・・」という事がアウトプットになります。
なので、ケースとしては複数ケースを用意する必要があります。その分テスト実施とアサインを考えていくとそういう調査に掛ける費用は膨らんでいきますし、ともすれば属性としての掛け合わせとして色んなパターンを考えていく必要がある場合にはユーザーテストを実施する事の時間も、費用も膨らみます。(一昔前はユーザーテストは100万掛かりますみたいな時代でしたね)
それでも、特定の人(選出された人)の感覚で行われる行動であり、それが一般的な行動なのかどうかすら実は確証がない。
だからこそ、Web上のデータ(GAなど)と照らし合わせもしつつユーザー行動としての整合性を考えていく必要もあったり、実はレポートした上でその後どう評価するかというのが難しいものでもあるというのが「ユーザーテスト」というものだったりします。
※因みに、弊社としてはそのユーザーテストを単体で見てる訳ではなく、その行動をカスタマージャーニーやWeb行動も踏まえた形で検証しておりますので是非お問合せください!
だったら、実際のWeb行動を抽出すればいいじゃない!
というのが、もうClarityのレコーディングという機能なのです。
↓画像クリックで動画で少し見れます!
こんな感じで、実際のサイト訪問者の方の動きがレコーディングされており、マウスの軌跡やクリック箇所、注視してみてるポイントなども手に取るようにわかってしまうのがこのClarityという機能の優れたポイントになります。
これまでの「こういう事をやってみてください」というシナリオに基づいたユーザーテストとは違い、実際のユーザー行動としてを分析することになるので所謂オーガニックな行動が確認できるというのが大きなポイントです。
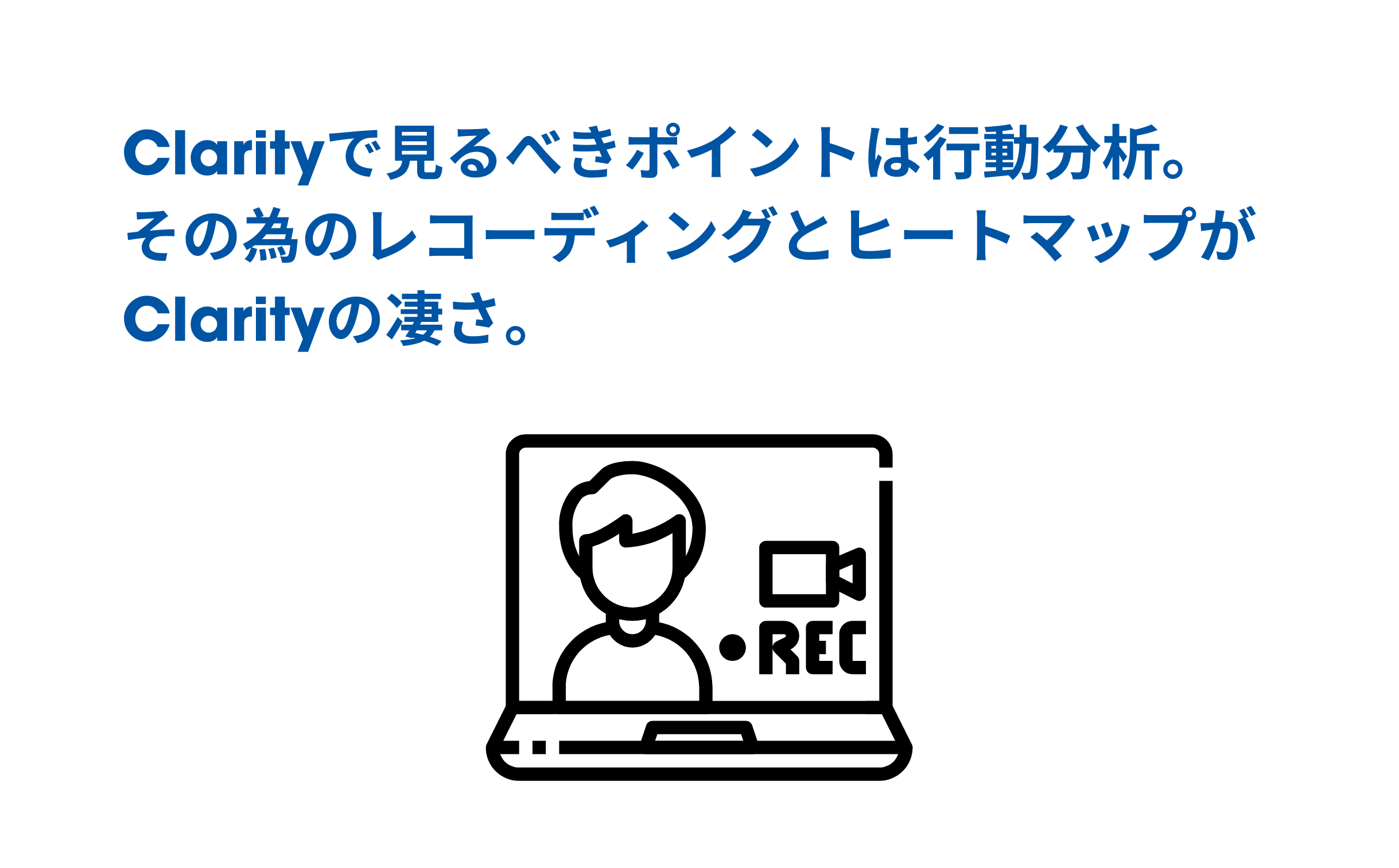
ついつい熱が入ってしまってレコーディングの話を先にしてしまいました。
ClarityはWebのユーザー行動分析に特化したツールです。
その為に、必要な機能としてレコーディングとヒートマップというものがあります。
レコーディングデータとしての凄さ
これは、言わずでもがなですが、先の動画のように「実際のユーザーのWeb上の行動が見える」というのは何よりも大きなポイントです。
ただ、膨大なサイトのアクセスセッションを一つ一つ見ていくには苦行しかない。と思います。
どうやって見るかは後に説明しますが、多機能なこのClarityのポイントになる機能を紹介します。
1、ソート・フィルタ機能
ざっと並べてみました。少しだけ説明していきます。
- 「ユーザー情報」
Clarityはデフォルト3日間のデータ表示となるので機関の設定、ブラウザの種類の設定、利用されてるデバイスなどでフィルタリングすることができますので、
例えば、スマホでのアクセスでうまくコンバージョンができてない時や、○○キャンペーンを実施したタイミングでのユーザー行動をその期間で検証したいなどを行う為にはこのフィルタリングが必要になります。
- 「トラフイィック」
トラフィクは、どのメディアからきているのか?をフィルタリングします。
例えば、広告流入しているユーザーとしてや検索エンジン流入してくるユーザーとして、それぞれで行動が変わってくるのでこのフィルタはユーザー行動の集客としてのポイントとして重要な項目になります。
先にあげてたキャンペーンはキャンペーンの設定をリンクURLとしてパラメーター設定しておけばこちらの値でもフィルタリングできますね。
- 「パス」
このパスというのも超重要です。(全部重要って言ってますね...)
よく、ユーザーテストなんかも「サイトのTOPページに来た人」ベースに行われることが多いのですが、それはちょっとテストとしては充分ではないと考えます。
皆さんのサイトのGoogleアナリティクスとかで「ランディングページ」という項目を見てもらったら分かるかと思いますが、TOPページから始まって流入している割合はサイト毎によって異なりますが8割9割がTOPページから始まってるなんてことは今まで相当数の会社さんのデータを見てきたんですがほぼありません。(特殊なサイトではあります)
5割、6割ぐらいが平均的なのではないでしょうか。寧ろ、オウンドメディアなんかをコーポレートサイトの同一サイト内で実施されてる会社さんはTOPがランディングページになってる割合なんて3割ぐらいであるなんてざらにあります。
Webサイトとしては見てもらいたいページという重点項目のページがあります。(目標設定をしっかり行われている場合には必ずKPIになってるはずです)
そのページを見てもらってるのかなどのポイントもユーザー行動としての見ていくべき指標になります。
なので、
「最初に訪れた」ページとしてのURL(パス)はどこからのユーザーであるか。(エントリURL)
「どのページを閲覧している」かをURLとして入力し、確認する(閲覧済みURL)
「どのページに辿り着いて終わってるか」(コンバージョンページへたどり着いた人たちの行動を検証する)(終了URL)
ざっとですが、上の行動以外にもシナリオとして考えられるケースというのが多々あると思いますのでそういうシナリオに沿ったページのフィルタリングができるという事だけ覚えてもらえればと思います!
- 「ページ」
こちらはよくある「滞在時間」のような概念と「クリックアクション」としての数値をフィルタリングします。
最も「行動」にとってはベースとなる指標にもなりますね。
〇分以上継続されているという事を指標にしたり(良いも悪いもありますが)、クリックを何回以上しているページであるか(行動であるか)という事を指標にしたりします。
ただ、人によっては(私はそうなんですが)ページを読んでるときに、テキストをドラッグして読む癖なかがある場合にはクリック数はとんでもなく多くなったりすることもあるのでそういうユーザーレコーディングは対象にしないなどの検討も必要になります。

セッション分析として、AIがこのレコーディングされてるユーザー行動をまとめてくれたりします。詳細分析というよりもサマリー分析ですが、何分もレコーディングデータを視聴して内容を確認することよりもこのサマリーを以て凡そを把握して、気になる部分はレコーディングデータとして詳細分析を行うなどの使い方が便利だなと考えております。
あくまでも分析と行動のまとめであって、改善部分はやはりもっと細かく分析する必要はあると感じてます。

これだけユーザー行動として赤裸々になってるという事は、その自分の行動が見られてるってことに不安を感じる人も居るかもしれません。
例えば入力フォームに住所氏名などを入れる箇所があるなどの場合にもマスクされてレコーディングデータとして録画されます。
アクセスするユーザーには接続時にClarityのIDは振られますが、個人を特定するような情報をそこには付与されないので安心して使えますね。
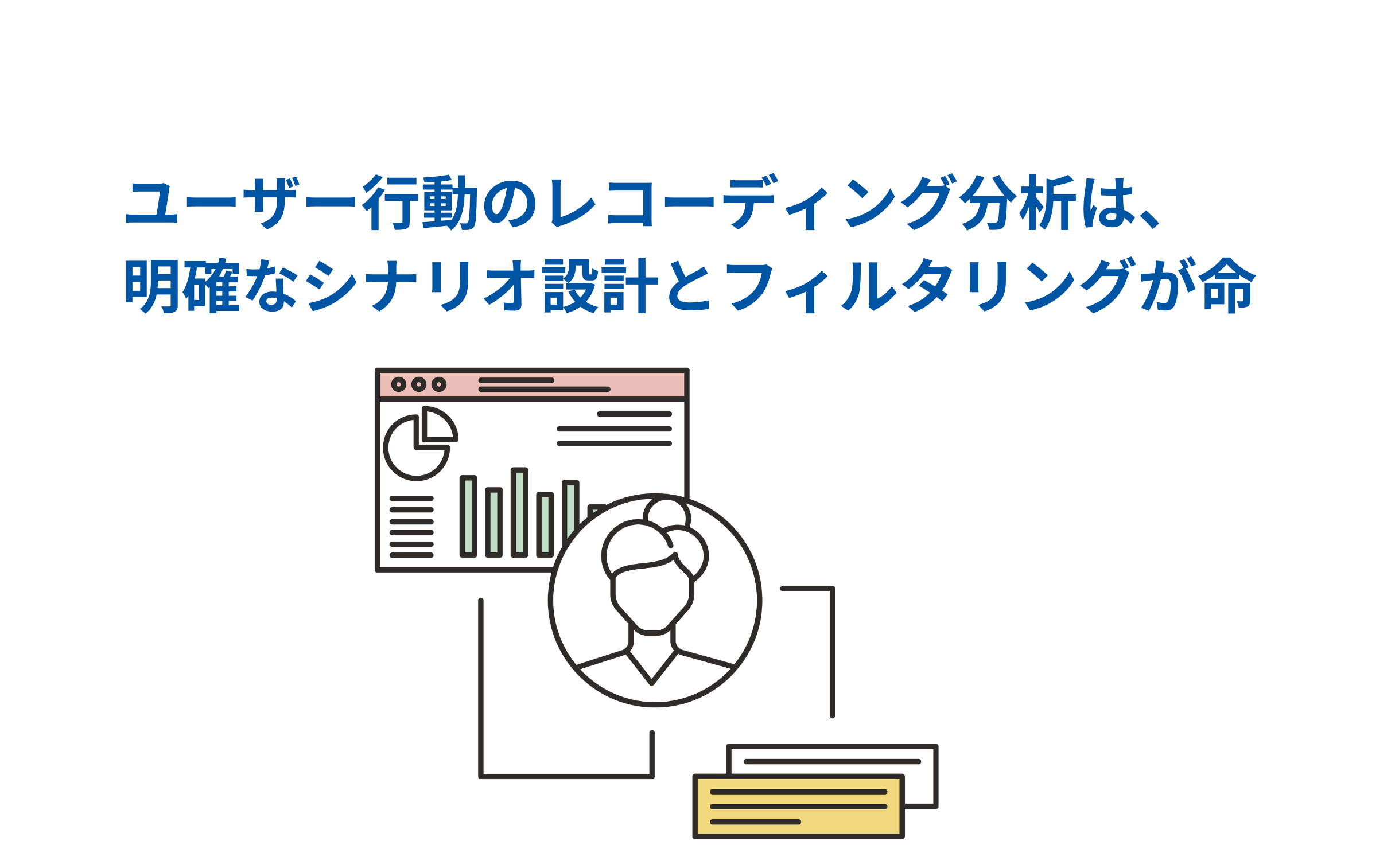
GoogleアナリティクスなどのWeb分析レポートも同じことを言えますが、ただ単にサマリーを見つめるだけの事なら何もそこに改善点は見つかりません。
レコーディングデータの確認は、しっかりと「ユーザー行動」の「何」を検証する為なのかという事をしっかりさせる必要があります。
ですが、なかなか皆様ご多忙な中で「かもしれない」というユーザーシナリオを設定して検証するのは時間が取れないと言われることも少なくありません。
勿論、そういう意味では我々フューチャースピリッツにご依頼していただくのが何よりもありがたいです!と、言ってしますのは簡単なのですが(そう言って終わりたいのですが笑)、折角この記事を書いてるのでアプローチの仕方も少しご紹介します。
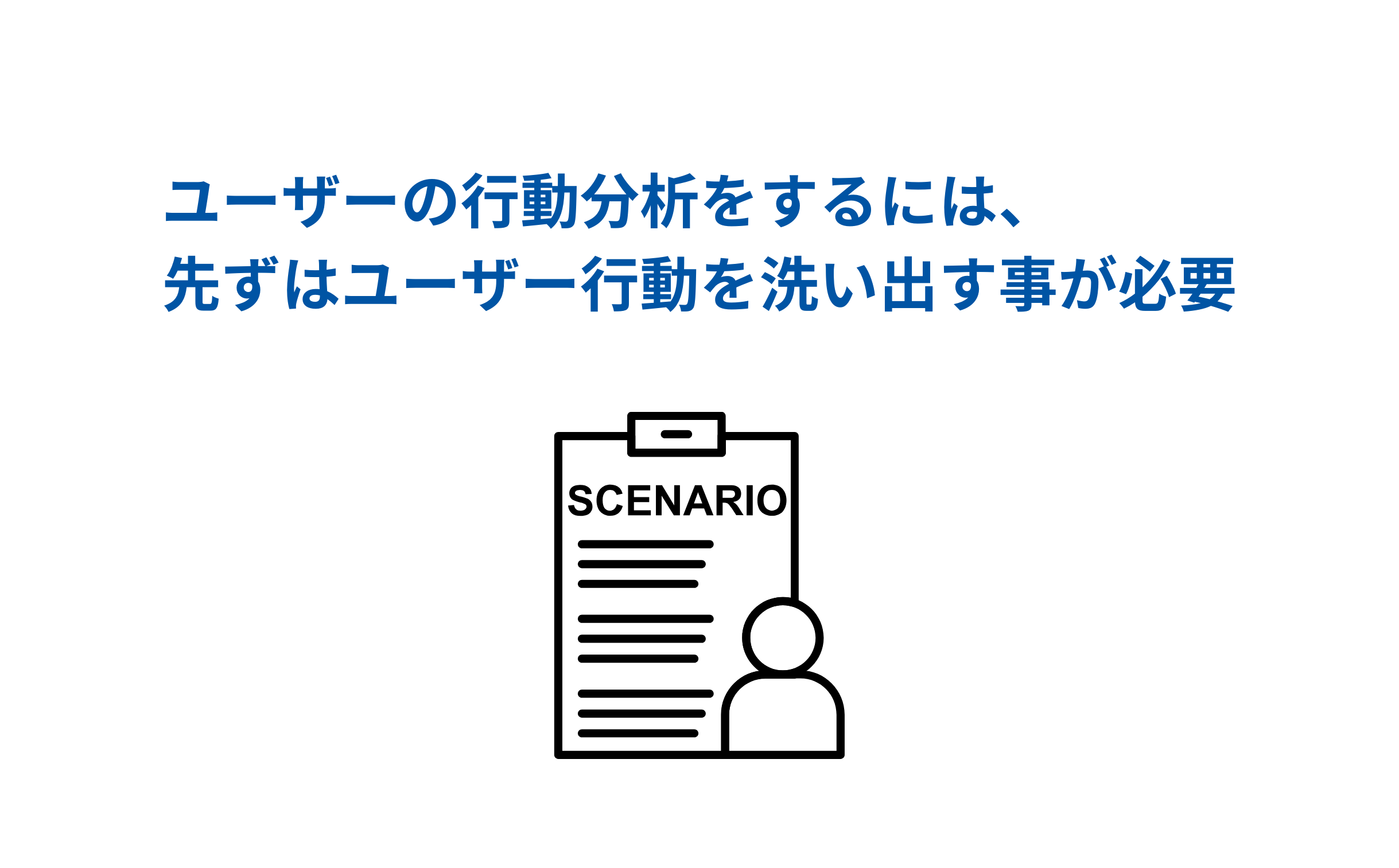
これは、ユーザーシナリオを書くという事。これに尽きます。
シナリオには、確認すべき行動が現れてきます。その行動を「評価」として行い、検証する部分をこういうツールとして利用することが重要です。
但し、この場合には「既存サイトをベースにユーザー行動をシナリオとして整理する」事になってくるのです。
これをやるには、そもそものWebサイトとしての顧客体験をどう捉え、ユーザーに対してのベネフィットは何なのか?KGIやKPIはどう設定しているのかという事が明確になってることが重要です。
半面、ここさえしっかりされていれば、シナリオも想定しやすいでしょう。そのままClarityでその行動の分析をしてしまえば完璧です。
但し、そこまで想定したKPIも無いとか、KPIとしての設定はしているものの思ってる効果を出せてない状態という場合には是非カスタマージャーニーから始めてみてください。
カスタマージャーニーを引ければ、その中からWebサイトとしてユーザーが求めている情報への行動が繋がってきます。
これをシナリオに落とし込むことができれば、そこからはWebサイト行動分析としてのClarityは十二分に真価を発揮してくれます!
カスタマージャーニーとユーザーシナリオについては、こんな記事も書かせてもらってますのでご紹介まで。
https://yorimiru.com/blog/2024/11/customerjourney.html

Clarityを難しく捉えるよりも、こういうツールっていうのは「視覚的に分かりやすい」っていう事が実は何よりも良いポイントだと思います。
こういうレコーディングデータであったり、今回紹介できてないですがヒートマップ機能(これは後日説明書きます)などは自分がマーケティングや解析をするという事に便利なツールという事だけではなく、周りの人やクライアント様などと同じものを見て、同じように感じて考えることができるというのが何よりも効果的な部分であり、そして、楽しい部分でもありますね!
私自身もお客様のClarityを管理させてもらって、一緒に見ながら楽しく報告させてもらったりしてます。
マーケティングなんていう言葉は小難しいと言ってらっしゃる皆さんの上司の方々などにこういうものを見てもらう事で先ずは興味を持ってもらえるようなツールという側面でもあると思っております。
そして、見ながら会話していると「こういうところがこうなってて欲しいんだよな」っていうお声をもらう事も多々あります。
これこそが、「共通認識」を作っていけること、そして、「お客様がこうなりたい」という想いを知れることに繋がります。
そういうものが何よりもマーケティングとして、大事な部分でもあり、我々がお客様のマーケティング支援としてお手伝いさせて頂く時に最も大事な部分だと考えてます。
-
資料請求
ヨリミルのサービス資料をダウンロードいただけます。
ノウハウをお役立ち資料として無料配布しています。 -
無料相談
課題感が明確でなくても構いません。
まずはお気軽にご相談ください。 -
メルマガ登録