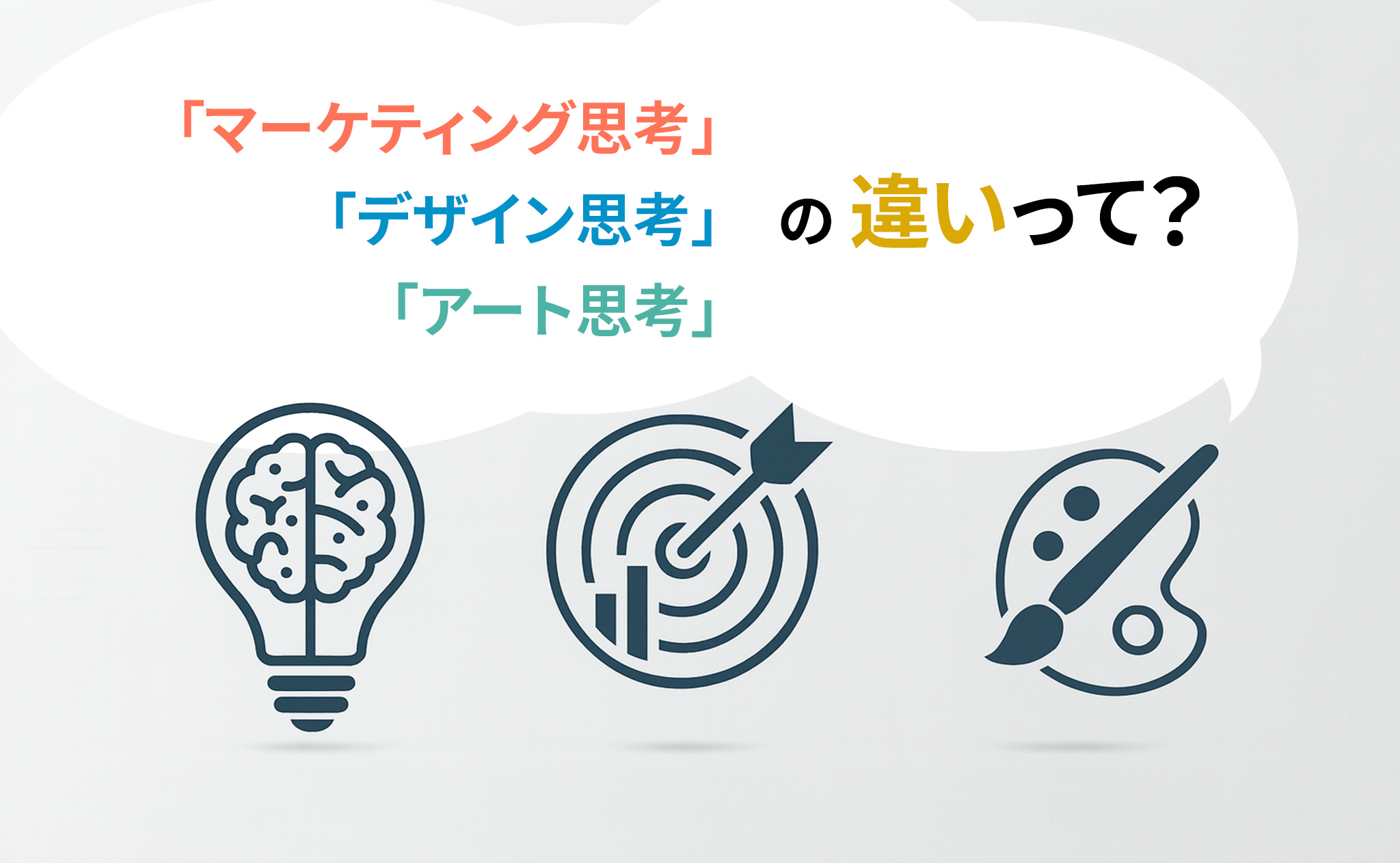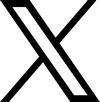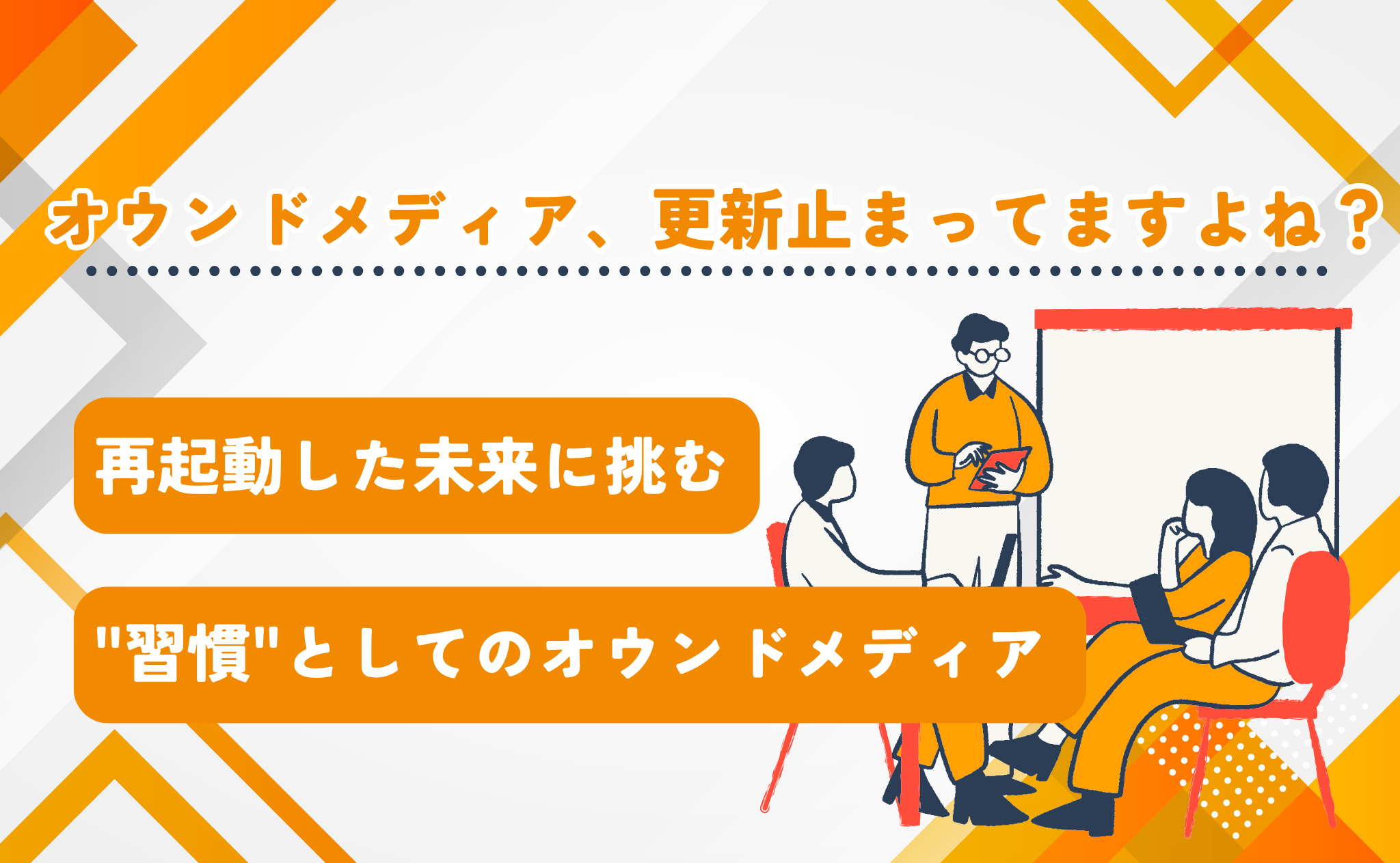「マーケティング思考」「デザイン思考」「アート思考」の違いって︖
「デザイン思考」との出会い
こんにちは。ヨリミルライターの佐藤です。
私は現在、webプロデュース部⾨に所属していますが、その前はデザイン会社で16年間デザイナーとしてカタログやパッケージ、web制作やECサイトの企画・運営などに携わってきました。当時はクライアントに対してヒアリングから企画・提案、クリエイティブ、保守・運営対応など全般を⼀⼈で⾏なっていました。⼩規模な会社だったため、上司や先輩に聞くということがあまりなく、試⾏錯誤しながら独⾃に解決策を模索しながら業務に取り組んでいました。
そして、「どうすればより良いデザインができるか」「どうすれば最適な問題解決ができるか」を考えている中で出会ったのが 「デザイン思考」でした。ユーザー中⼼で課題を捉え、解決へと導くプロセスは、⾃分の仕事観やスタイルにフィットするものでした。
マーケティング・デザイン・アートの三思考で導く価値創造

しかし、より良いデザインをしたいと思った時に、それだけでは最適解に辿り着かないと感じ、マーケティングや経営など幅広い知⾒が必要だと考えました。そこから現在の会社に転職し、「マーケティング思考」や「アート思考」というものを知り、より多⾓的な視点からヒアリング・提案・クリエイティブを⼼がけるようになりました。
マーケティング思考とは
1900年代初頭〜1950年代の⼤量⽣産期、企業の関⼼は「いかに効率よく作り、⼤量に売るか」に集まっていました。しかし市場が成熟し、消費者が「⾃分に合ったもの」を求めるようになると、単なる供給だけでは選ばれなくなります。ここで重要となったのが 「マーケティング思考」です。
マーケティング思考は、市場や顧客を起点に考え、彼らの課題や欲求を理解したうえで最適な価値を提供する考え⽅です。のこと。例えば、保険商品や通信サービスのように「複雑で分かりにくい」と敬遠されがちなものでも、顧客が本当に知りたい情報をシンプルに整理し、安⼼して選べるように可視化することで、⼤きな信頼を得られるようになります。
Web制作では、市場や顧客ニーズから出発し、競合分析やペルソナ設計を経て、独⾃価値(USP)を構築するプロセスです。
KBOツリーマップやカスタマージャーニーを活⽤して、施策の全体像をチームと共有し、クライアントと「誰に、何を、どう伝えるか」を明確にします。これにより、デザインとマーケティング施策が⼀貫性を持ち、成果につながります。
つまりマーケティング思考とは、「どう作るか」ではなく「誰に、どんな価値を届けるか」を起点に戦略を設計するアプローチです。市場分析や競合分析を踏まえ、顧客像(ペルソナ)を描き、その⼈の体験全体を設計していくことが本質といえるでしょう。
デザイン思考とは
1960年代〜2000年代前半の多様化・競争激化期において、企業は「良い商品を作れば売れる」という単純な構図から抜け出す必要に迫られました。市場にモノがあふれ、消費者は選択肢を⽐較しながら「どれが⾃分にとって⼼地よいか」を基準に選ぶようになったからです。
この流れの中で重視されるようになったのが「デザイン思考」です。デザイン思考はユーザー中⼼の課題解決アプローチであり、消費者の⾏動や感情に深く共感しながら、本質的なニーズを掘り下げて解決策を導く⽅法論です。
例えば「操作はできるが使いにくい」「⾒た⽬は良いが不安が残る」といった状況でも、ユーザーの体験を徹底的に観察・分析し、試作品を作って検証を重ねることで、単なる機能や形ではなく「体験としての価値」を提供できるようになります。
Web制作でも、まずは「誰のために作るのか」を徹底的に掘り下げ、アクセス解析やインタビューだけでなく、実際の利⽤シーンを想像できるプロトタイプを作成し、ユーザー⽬線で検証します。これにより、⾒た⽬だけではない「体験としてのデザイン」が可能になります。
つまりデザイン思考とは、競争が激化した時代において「ユーザーに寄り添い、共感から発想する」ことで差別化を⽣み出すアプローチなのです。
アート思考とは
2000年代半ば以降の成熟・コモディティ化期において、多くの製品やサービスは機能や品質での差別化が難しくなりました。消費者が求めるのは「便利さ」や「安さ」だけではなく、世界観や体験価値といった感性的な要素へと広がっていったのです。
この時代においても、ユーザー中⼼で課題を解決する「デザイン思考」は依然として有⽤でした。使いやすさや快適さを徹底的に磨き、顧客体験の摩擦をなくす取り組みは確かな成果を⽣み出し続けたのです。しかし、それだけでは模倣や代替が容易であり、持続的な差別化には限界がありました。
そこで注⽬されたのが、感性や直感を起点に独⾃の価値を創出する「アート思考」です。データやユーザー調査からは⾒えにくい「新しい意味」や「社会に提⽰するビジョン」を形にすることで、ブランドやサービスに独⾃の世界観を与え、単なる機能や価格競争を超えた価値を⽣み出そうとしたのです。
Web制作では、数字で説明できる価値だけでなく、世界観や物語をどう表現するか、サイト全体のビジュアルトーンや写真選定、キャッチコピーまで含めて「感情を動かす仕掛け」を設計します。それは、ただ情報を届けるだけでなく、「記憶に残る体験」を提供するためです。
さらに2010年代半ばからの予測不能なVUCA時代においても、過去のデータや既存の枠組みだけでは未来を描けない場⾯が増えました。正解のない課題に向き合うためには、論理や分析にとどまらず、ビジョンや物語を描き、共感を⽣み出す⼒が求められます。そのアプローチを可能にするのが、アート思考なのです。
ビジュアライゼーションは「課題を共有する⾔語」

Web制作の現場では、クライアントの課題や要望をどう共有し、形にしていくかが常に問われます。そこで役⽴つのが「ビジュアライゼーション=可視化」です。数字や⾔葉では抽象的な情報を、図解やマップ、プロトタイプに落とし込むことで、関係者全員が同じ景⾊を⾒ながら議論できるようになります。市場の構造や顧客の⾏動、競合との位置関係を可視化することで、どこに差別化の余地があるのか、どの層を狙うべきかが具体的に⾒えてきます。この「可視化の⼒」を、デザイン・マーケティング・アートという3つの思考法を総合的に活⽤しているのが『ヨリミル』だと思っています。
現代におけるさまざまな思考法
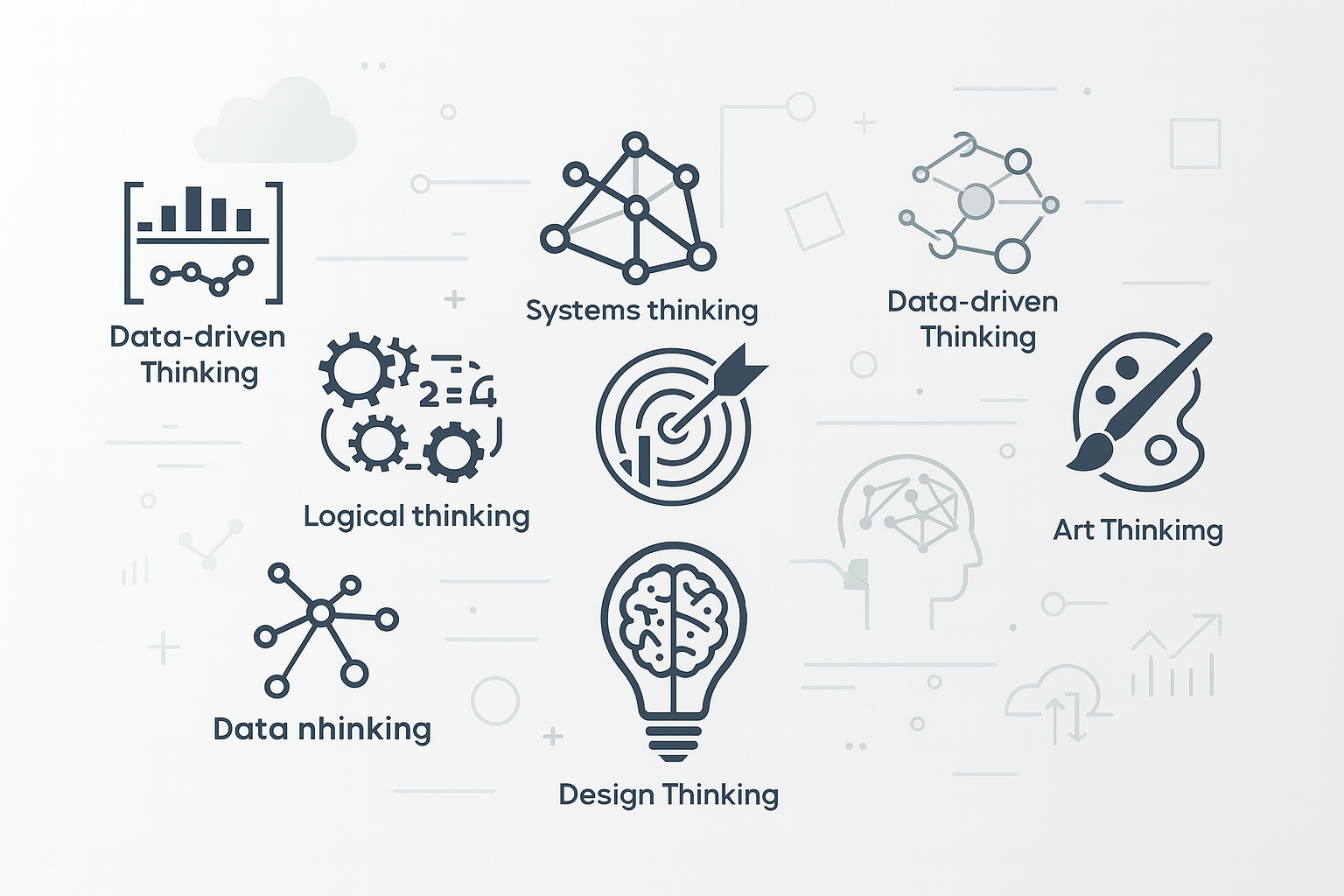
デザイン思考・マーケティング思考・アート思考が価値創造の⼤きな柱である⼀⽅、近年のビジネス環境では、それを補完する多様な思考法も誕⽣しています。
-
ロジカルシンキング
事実やデータを整理し、因果関係を明確にする思考法です。情報を体系的に構造化することで、抜けや重複を防ぎ、結論までの筋道を誰もが理解できる形に整えます。これにより、社内外の関係者との合意形成や意思決定がスムーズになります。
- システム思考
物事を部分ではなく全体として捉え、要素間の相互作⽤やフィードバックループを理解する⽅法です。施策が及ぼす⻑期的 な影響や、副作⽤的な変化を予測できるため、持続可能な戦略設計に役⽴ちます。
-
データドリブン思考
経験や直感に頼るのではなく、定量的なデータに基づいて判断を下す考え⽅です。KPI設計やA/Bテストなどを活⽤し、施策の効果を客観的に検証することで、再現性の⾼い改善サイクルを回すことができます。
-
AI-First思考
近年特に重要性を増しているのが、AIを前提に発想する思考法です。⽣成AIや解析AIを活⽤して業務フローを効率化するだけでなく、⼈とAIの役割分担を再設計し、新しい価値を創り出すことを⽬的としています。
これらの思考法は、例えば、ロジカルシンキングで整理した情報をシステム思考で全体最適の視点から⾒直し、さらにデータドリブン思考で検証を重ねる。そこにAI-First思考を組み合わせるといった、使い⽅も考えられますね。
おわりに
思考法は単独でも有効ですが、組み合わせることでより⼤きな⼒を発揮します。ただし、それぞれの思考法をいきなり実践しようとすると難しく、どこから⼿を付ければよいのか迷うことも少なくありません。
私たちの『ヨリミル』は、こうした思考法を実際のプロジェクトで活かしながら、課題を可視化し、最適な解決策を導き出す仕組みです。さまざまな業種のクライアントと共に実践を重ねてきたからこそ、安⼼して取り組めるプロセスがあります。
ぜひ⼀緒に『ヨリミル』を通じて、多様な思考法を活⽤しながら新しい価値を⽣み出していきませんか。
-
資料請求
ヨリミルのサービス資料をダウンロードいただけます。
ノウハウをお役立ち資料として無料配布しています。 -
無料相談
課題感が明確でなくても構いません。
まずはお気軽にご相談ください。 -
メルマガ登録