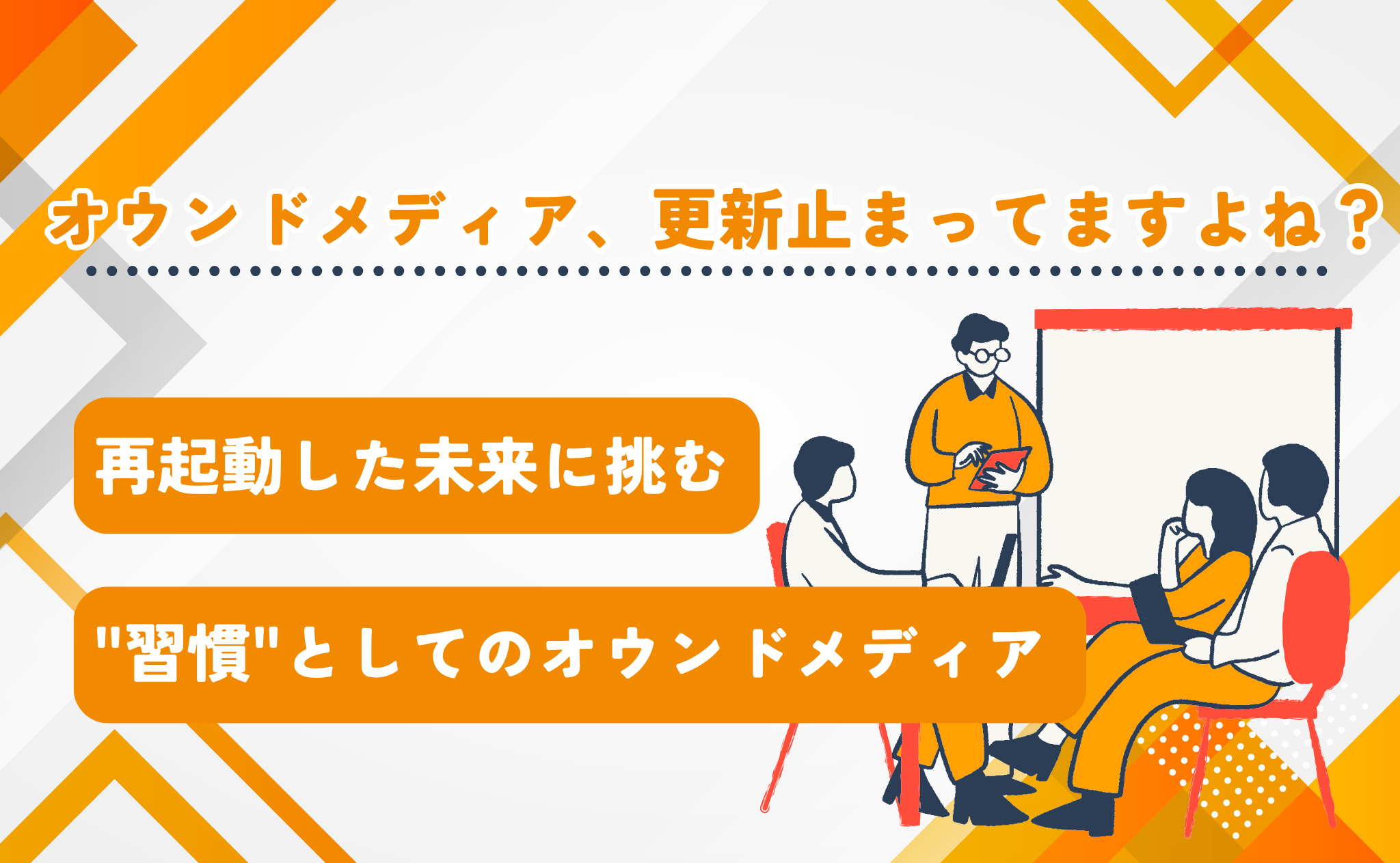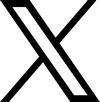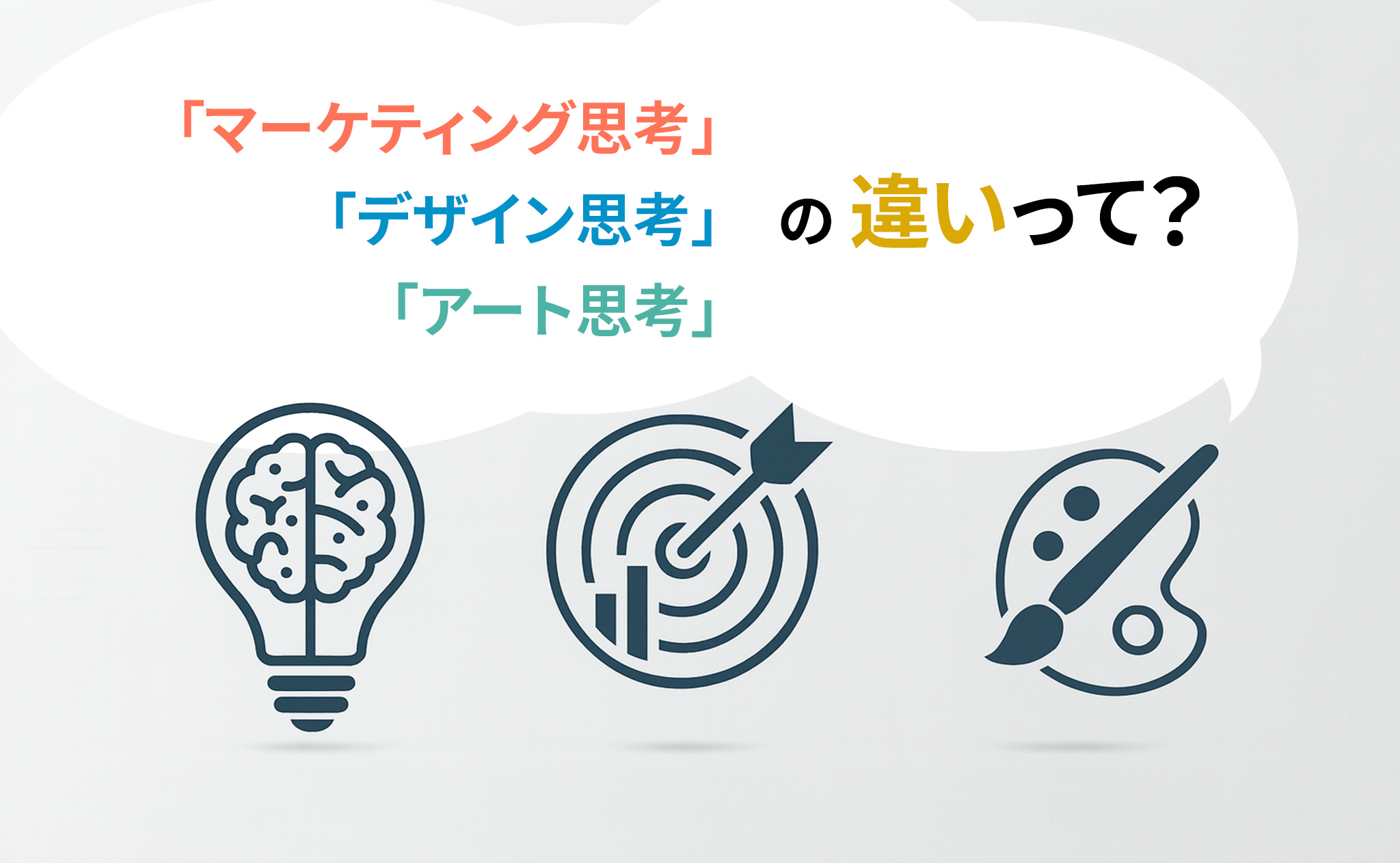オウンドメディア、更新止まってますよね?──再起動した未来に挑む"習慣"としてのオウンドメディア
こんにちは、ヨリミルライターの高村です。
生成AIの進化が激しさを増す現代、企業が「自分たちの言葉」で顧客や社会とつながるオウンドメディアの価値は、ますます大きくなっています。しかし現実には、多くの企業がその価値を十分に引き出せず、更新が止まってしまう――私たちもその壁に直面しました。
本記事では、更新停止からいかに脱却し、「未来を創る習慣」として再起動したか。そのプロセスと気づきを、私自身の体験を軸に、未来志向の視点でお伝えします。もし貴社のメディアが同じ課題を抱えているなら、この物語が新たな一歩の後押しとなれば幸いです。
1.更新が止まる本当の理由:見えない三大ハードル

属人的テーマ設定による共有知化の阻害
社内メンバーでライターしていくスタイルを取りましたが、書き手の専門性や個性に頼るテーマ設計は、他のメンバーにとって「自分ごと化」しづらくなり、コンテンツの継続的生成を難しくします。知見の属人化は、組織全体のナレッジ資産としての蓄積を妨ぎました。
完璧主義が生む心理的障壁
立ち上げ当初から記事の質など外部指標に縛られ過ぎると、「まず書く」という挑戦の芽が摘まれます。創造性と挑戦を支えるはずの環境が、かえって「失敗できない」という無言の圧力に変わりがちです。
「なぜ書くのか」の目的共有不足
オウンドメディアが組織や顧客にどんな価値をもたらすか、明確な目的が浸透していなければ、どんなに重要な活動でも日々の業務に埋もれてしまいます。優先順位が下がることで、結果的に更新の手が止まってしまうのです。
2.再起動の設計思想 「柔らかな枠」とAI時代の新しい習慣

私たちが選んだのは、厳格なルールや型にはめるのではなく、誰もが自発的に関われる柔らかな枠をつくることでした。これが「未来を創る習慣」へ進化する鍵となりました。
テーマ設計 「社内の日常 × 未来志向」の二軸
業務現場の気づきや、未来への挑戦をテーマに据え、「飲み会幹事のコツ」や「田舎暮らしのリアル」など、専門家でなくても書ける題材を推奨。多様な視点と安心感が生まれ、メンバーが自然体で参加できる土壌が醸成されました。
生成AIを編集パートナーとして活用
AIで初稿のたたき台、AIで表現の微調整、AIデザインツールでビジュアル統一。各種AIツールを組み合わせることで「書き始めから公開までの心理的距離」を大幅に短縮。ITリテラシーの高い組織文化と相まって、誰もが「まずやってみる」一歩を踏み出しやすくなりました。
管理シート文化からドラフト投稿文化への転換
Excelによる進行管理をやめ、CMSの下書き・コメント欄を活用したカジュアルなフィードバック体制に。これにより「まず1時間で下書きを上げてみる」というスピード感が組織に浸透し、月1本から週1本以上への更新頻度アップを実現しました。
3.無駄が生む価値 共感と信頼、未来への投資

「効率」や「成果」ばかりが重視されがちな現代ですが、一見無駄に見えるコンテンツこそ、実は計り知れない価値を生みます。
らしさ"のにじむ記事が、カルチャーの共感を呼ぶ
何気ない記事──たとえば、「田舎暮らしのリアル」や、あるメンバーが「飲み会の幹事で気をつけたこと」、あるいは業務にちょっと関係ある「ゆるい考察」など。そんな雑談のような投稿が、実は一番読まれていたりします。それはきっと、「どんな人たちが、どんな空気で働いているのか」が伝わるから。公式サイトで見る「理念」ではわからない、空気感や温度こそが、共感を生むのだと思います。
「こういう人たちに仕事を依頼してみたいかも。こういう人たちと一緒に働きたいかも」
オウンドメディアには、そうした「文化の解像度」を上げる役割もあると信じています。
"本音と誠実さ"が信頼をつくる
オウンドメディアの中には、自社の成功体験だけでなく、ときには「失敗談」などのエピソードも含まれています。一見すると、自分たちの価値を下げるようにも見えるこれらの発信。でも実は、それこそが信頼の種になると感じています。
私たちは、お客さまの課題解決を第一に考えています。だからこそ、「それは今やるべきではないかもしれません」と伝えることもあるし、「もっと適したパートナーが他にいるかもしれません」と話すこともあります。
そういった"本音"があるからこそ、後から「あのとき誠実だった会社」として思い出してもらえたり、紹介が生まれたりする。マーケティングは、目先の売上だけじゃなく、こうした小さな信頼の積み重ねが将来のビジネスをつくっていくのだと、改めて実感しています。
4.未来につなげる"ゆるい習慣"のデザイン
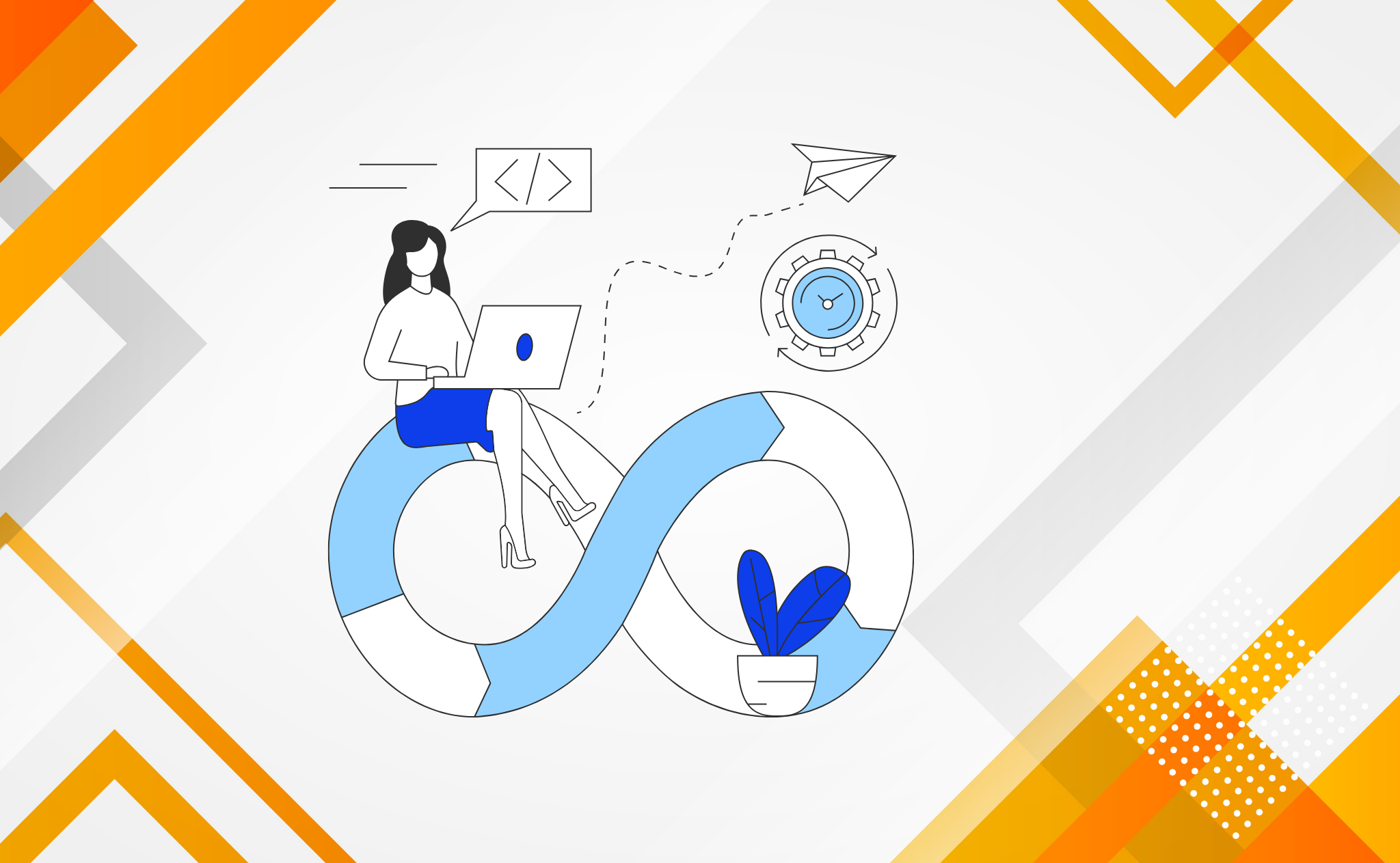
メディア運営を単発のプロジェクトで終わらせず、持続可能な資産に育てるには、「KPI」より「続ける歓び」をどう設計するかがカギです。
継続自体を評価対象に組み込む文化
月次MVPの選定基準を「PV」から「投稿本数」や「新規チャレンジ」など挑戦回数重視に変更。完璧主義から解放され、気軽に発信しやすい空気が生まれました。
70点公開・必要であれば後日アップデート
完璧を待たずにまずは公開を目指し、読者の反応やデータを基に改善していくアジャイル型運営を導入。PDCAサイクルの高速化で、組織全体の学習する力が強化されました。
心理的安全性と本音・失敗談の歓迎
失敗談や葛藤も含め率直に語ることを歓迎し、ネガティブな体験こそ組織成長の燃料という認識を醸成。安心して本音を出せる環境が、魅力的なコンテンツの源泉となっています。
こうした無理のない習慣づけが、すぐに見える成果だけでなく、長く選ばれ続ける信頼やつながりの土台になっていきます。
まとめ 無駄と本音が生む、オウンドメディアの未来価値

オウンドメディアの更新停止は、決して失敗ではなく、進化のシグナルです。再起動の第一歩は、「意味があるか」より「心が動くか」「書きたいか」を問い直すこと。書き手がワクワクできる余白を残し、AIや新しい習慣を柔軟に取り入れれば、メディアは必ず息を吹き返します。
オウンドメディアは、短期KPIを超えて、未来の信頼残高を積み上げる装置です。一見無駄に見える記事も、本音をさらけ出す記事も、すべてがブランドの重力を強める微粒子。もし今、更新ボタンに指が伸び悩んでいるなら、今日この瞬間、小さくても心が動くネタを下書きしてみてください。その一歩が、未来の顧客、仲間、市場との豊かな対話を開く確かなトリガーになるはずです。
-
資料請求
ヨリミルのサービス資料をダウンロードいただけます。
ノウハウをお役立ち資料として無料配布しています。 -
無料相談
課題感が明確でなくても構いません。
まずはお気軽にご相談ください。 -
メルマガ登録